環境問題に強い関心を抱き、夢を叶えるために努力し続ける任さんのお話(横浜市で暮らす外国人トークリレー/第9回)
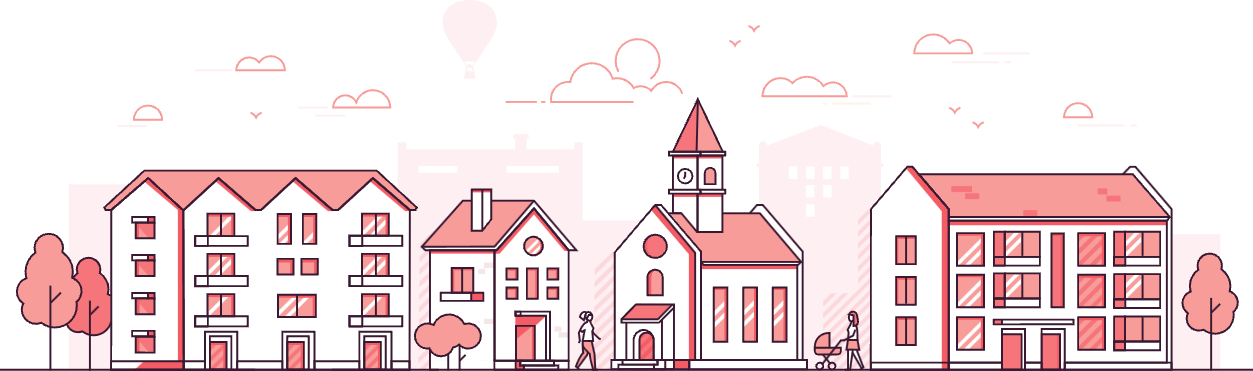
外国につながる皆さんに、生活の中での日本語との関わりについて話していただくコーナーです。
今回登場するのは、環境学を学ぶ留学生(大学4年)の任さん。来日当初は「あいうえお」もままならなかったそうですが、とても流暢な日本語でインタビューに応じてくださいました。幼少期の経験から環境問題に強い関心を抱き、夢を叶えるために努力し続けています。

任 金龍(にん きんりゅう)さん
中国出身/日本に住んで5年
横浜市国際学生会館(*)2022年度留学生会会長に就任し、学生たちの「交流」の場をつくるため、イベント企画などの活動をしています。趣味はバスケットボールで、会館施設内のコートで汗を流してリフレッシュしているそうです。 明るく何事にも前向きで、明確なビジョンを持って楽しく過ごされているのがとても印象的でした。
(*)横浜市国際学生会館:外国人の留学生、研究者等に宿泊施設を提供するとともに、市民の国際理解を推進するために設置された会館。指定管理者はYOKE。
日本に来た理由を教えてください
約15年前、住んでいた村が鉱山の開発により環境汚染され、家族で南京へ移住しました。幼少期より環境問題と隣り合わせだった私は、環境技術が先進的な日本で学びたいと考え、日本への留学を決めました。
大学では環境学を専攻し、基礎知識の習得はもちろん、「環境保全と経済成長を両立させる」という観点から、経営の知識も深めています。環境問題は経済活動などの人間の営みにより発生してしまいますが、国や地域の発展のため、その活動を止めることはできません。とても難しい課題ですが、今学んでいる知識を最大限に吸収し、今後に活かしていきたいと思います。
どのように日本語を勉強してきましたか
日本語学校にも通いましたが、中でもグンと日本語力が伸びたと感じるのは、ファーストフード店でのアルバイト経験です。
はじめは伝わらないことばかりでしたが、失敗を恐れずに、日本人スタッフに積極的に話しかけるようにしました。また、少しでも多くの会話ができるよう、きれいな文法よりも、とくにかくたくさんの単語を覚えるよう心がけました。それ以外にも、スタッフとの会話を事前にシミュレーションし、鏡の前で会話の練習(1人2役)をしたりしました。職場の雰囲気もとても温かく、スタッフだけでなく店長も、シンプルな日本語で私とのコミュニケーションを楽しんでくれて、嬉しかったです。
日本語の勉強を続ける秘訣はありますか
日本語を勉強する「目的」を明確にすることと、しっかり「リフレッシュ」することが続けていく秘訣だと思います。私の場合は、環境学を学ぶために日本に来たので、その時々で取り組んでいること・頑張ってることのベストを尽くしたいという思いで日本語を勉強してきました。モチベーションが下がったときは、大好きなラーメンを食べたり、バスケットボールをして乗り切りました。
日本・中国での就職活動、それぞれの違いは?
約半年間、両国で就職活動をしましたが、求められる人材像がまったく異なると感じました。日本では人柄、将来性が重視され、スキルはそれほど必要とされないことが多いようです。また、入社後の研修が充実しているため、志望者にとってはチャンスが大きいと言えます。
一方の中国では、即戦力となる人材が最も求められる傾向にあります。このような背景から、中国の大学生は2年生から積極的にインターンシップに参加し、企業の研修も入社前に行われるのが通例となっています。加えて勉強量も多いため、趣味や他の勉強に費やす時間はあまり無いようです。私は勉強も趣味も両立できているので、とても嬉しいです。人生一度きりなので、大変なことでも挑戦し、悔いのない学生生活を送りたいと思います。
任さんの、将来のビジョンを教えてください
当初は日本で就職したいと考えていましたが、家族のために中国で働くことを決めました。来年4月より、上海にある日系企業で、経営コンサルタントとして働く予定です。そこでしっかりと経営の実務経験を積み、将来的には、電気自動車普及のビジネスをしている父とともに、脱炭素社会を目指した仕事をしたいと思っています。
(掲載誌:情報冊子「にほんごコミュニケ―ション」2022年7月号)


