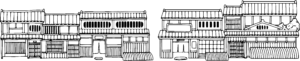連載② 難民を支える支援とは ~第2回:受入れ後の支援を考える(情報冊子 2022年11月号掲載)

日本に暮らす難民への理解を深めていただくための連載(全3回)です。
矢崎理恵さん(社会福祉法人 さぽうと21)に執筆いただきました。
第2回:受け入れ後の支援を考える
前回は国内における難民受入れの変遷、難民認定について触れましたが、受入れ後に必要となる「支援」にはどのようなものがあるのでしょうか。その「支援」は、今日明日の衣食住を支える支援から、長い時間をかけた自立支援まで、多岐にわたります。
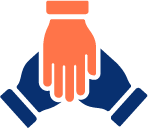
さまざまな支援のかたち
難民の形態などによって受けられる支援の形は変わります。いずれにおいても、地域の団体や学校、職場、地域の人たちが、ともに共生社会を築き上げていく姿勢が必要です。
01.来日直後の支援
■第三国定住難民の場合
日本政府の主導で進められる「第三国定住難民」の場合は、来日直後から約6カ月におよぶ「定住支援プログラム」を受けることになります。572授業時限の日本語教育と、120授業時限の生活ガイダンスが提供されます。来日直後のタイミングで行われる、必要不可欠な「支援」です。
■条約難民の場合
難民認定の審査を受けるべく難民申請から始める方々が前述の支援を受けられるのは、審査の結果が出た後です。まずは申請書類の準備を進めながら、「食べる物」「住む所」「着る物」の心配をしなければなりません。食料やシェルターの提供など、そこに手を差し伸べる活動をする団体もあります。また、就労に備えて、日本語学習の機会を提供する団体もあります。ただ、そうした支援の情報に、誰もが行きつけるわけではありません。
02.定住生活に向けた支援
晴れて難民認定されたとしても、それはゴールではなくスタートです。故郷を失い、ありふれた日常を失い、ときに家族や仲間を失った人々が、制度も言葉も異なる国で、ゼロから自立した生活を目指さなければなりません。「生活支援」「就労支援」「子ども若者への教育支援」は欠かせないものであり、その全てに関わってくるのは「日本語学習支援」です。
支援団体は定住支援のプロとして、煩雑な役所の手続きや家探し、職探しの支援を進めていきます。さらには、日本語学習の手だてを模索します。公的な既存の支援につなげながら、時間をかけて、難民の方々自身が納得しながら前に進んでいけるよう伴走を続けます。
難民支援の現場から ~長い道のり~

(Cさん)
10代後半で来日し、難民申請中に無料の地域日本語教室で懸命に学び続けました。難民認定された20代後半には、夢だった大学進学を果たしました。今は難民支援の活動に勤しんでいます。

(Rさん)
申請中に支援団体の紹介でゼロからプログラミングを学び始めました。今は、プログラマーとして活躍し、最近、母国の子ども達にオンラインでプログラミングを教えるようになりました。

(Nさん)
子育てが少し落ち着いたころにネイリストを目指し勉強しました。夢をあきらめずに努力し7年経ったころ、自分の店をもちました。今は後輩の指導に余念がありません。
長い道のりです。でも、多くの方が、小さな機会を大切に自分の中で育て、努力を重ね、今を生きています。そんな皆さんの日常を支えているのは、支援団体ではなく、ご近所や職場の方、学校の友達や先生方です。さりげなく交わす日常の一言が、何ものにも代えがたい大きな力になっていることを、地域の皆さんに知っていただきたいと日々感じています。
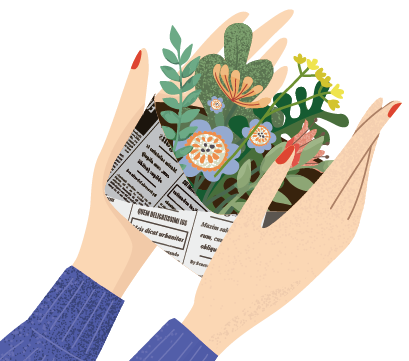

次回(最終回)は、地域で共に暮らしていくことについて考えます。