「働く場」をとおして、つながる~異文化間コミュニケーション(情報冊子 2022年3月号掲載)

「外国人を雇用しているけれど、話がなかなか伝わらない」
「雇用を検討しているけれど、どのような準備をすれば良いのか分からない」
…このような悩みを抱える企業も少なくないでしょう。
今回は、そのような課題を解決し、職場での異文化間コミュニケーションを円滑にするサポートを行うお2人にお話を伺いました。
*この記事は、インタビュー内容をもとにYOKEが再編成し記事を掲載しています。
異文化間のコミュニケーション、大切なことは?
外国人を雇用している企業の方から、「外国人従業員がこちらの伝えたいことをなかなか理解してくれない」という話をよく聞きます。コミュニケーションのすれ違いは、ことばの問題だけなのでしょうか?
お話をうかがったのは…
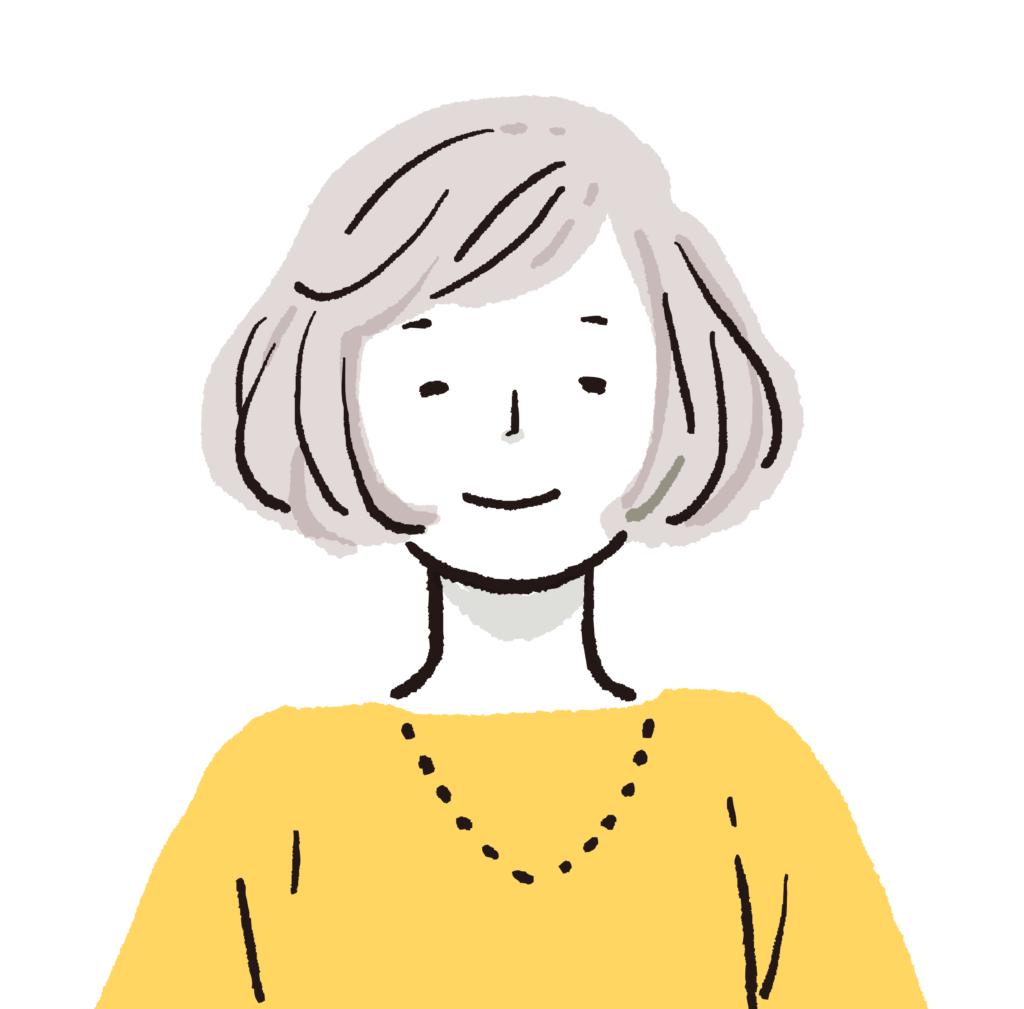
株式会社インカレックス
取締役・代表講師 AYAさん
外国人材受け入れ企業に対するサポート事業や外国人従業員への日本語やビジネスマナーの研修を行う。
コミュニケーションは互いの理解から
外国人を雇用している企業の方向けに実施している「異文化間コミュニケーション研修」は、まず外国人従業員の立場に立ち、異文化やミスコミュニケーションを体感してもらうことから始まります。はじめに体感することで多くの気付きがあり、すれ違いの原因は異文化間で起きる考え方の違いだということが理解しやすくなるためです。
一例を挙げると、中国と日本は、世界の中ではコミュニケーションの取り方が比較的近いと考えられていますが、二国間を細かく比べてみると、やはりさまざまな違いがあります。以前、日本語力には全く心配がない中国の方が、この研修を受けた後で「今までなぜ上手くいかなかったのかがよくわかった。」と言っていたそうです。
研修に込められた思い
研修を進めるうちに、多くの受け入れ企業の方が日本語の難しさに改めて気づき、外国人従業員の努力を応援する気持ちになっていくようです。そして、「聴き手責任型のコミュニケーション」から、「話し手責任型のコミュニケーション」に考え方を変えていく傾向にあります。
研修タイトル中の「間」は、単に異文化を知るだけにとどまらず、両者の間で起こっていることを理解し、やさしい日本語などのツールを身につけ、お互いに歩み寄り、つながっていきましょうという気持ちが込められています。これまで研修を行ったのは人材派遣、宿泊、IT業界などの企業が中心でしたが、今後さまざまな業種で必要とされていくと思っています。
外国人従業員とともに、より良い職場にしていくには?
経営者や日本人の社員などから、「職場でともに働く外国人従業員に日本語を学んでほしい」との声を聴くことは少なくありません。 企業にとって、また働くすべての従業員にとって、外国人従業員 の日本語学習をどのように位置づけ、取組を進めていくとよいのでしょうか?
お話をうかがったのは…

内定ブリッジ株式会社
代表取締役 淺海一郎さん
厚労省(MHLW)「外国人の能力開発に関する専門研修」検討委員会委員など
大切なのは「全従業員の共通理解」
外国人従業員を対象とした日本語教室のニーズは、製造業の盛んな地域をはじめ、各地で高まりつつあります。当社で実施しているライブ型オンライン日本語教室の場合、参加している外国人従業員が職場からの帰宅途中でも参加するなど、学習意欲の高さも見られます。そうしたモチベーションを維持していくためには、ただ「日本語を勉強しなさい」と言うのではなく、日本語を学ぶことが仕事に役立つのだという、職場全体の共通理解がとても重要になってきます。
まず、外国人従業員支援が、企業にとってどのようなメリットがあるのかを具体的に共有します。そのうえで、各職場で外国人従業員に学んでほしい日本語について、具体的な場面や、ゴールを明確化します。さらに、日本語力の向上などさまざまな変化に対し、同僚や上司がその変化を認めことばで伝えることが、モチベーションの維持には欠かせません。
より良い意識改革へとつなげる
外国人従業員支援は、日本人従業員支援にもつながります。日本人従業員が外国人従業員に分かりやすいよう、日本語の使い方や表現を調整・工夫することでコミュニケーションは円滑化し、自身のストレスも減らすことになります。わかりやすい日本語やコミュニケーションを工夫することで、誰にとっても働きやすい職場になります。最初は外国人との間にある異文化の「異」なる部分に意識が行きがちですが、取組が進むにつれてその意識は必ず変わります。
将来的には就業規則の多言語化や、外国人従業員の日本語の上達なども評価に含めた人事評価制度の検討等、さまざまな取り組みが考えられます。ぜひ、当事者意識をもって、従業員一人一人が自身の働く企業をより良くするための発想をもち、外国人従業員とともに働く職場づくりに共に取組んでいきましょう。

「日本で働く外国人従業員にとって、一日の長い時間を過ごす働く場でお互いに歩み寄りつながりを持てるということは、日本の生活が充実することそのものです。お二人の話を伺って、職場での一人ひとりの気づきと共通理解の大切さを実感しました。


