連載③ 難民を支える支援とは ~最終回:地域で共に暮らしていく(情報冊子 2023年3月号掲載)

日本に暮らす難民への理解を深めていただくための連載(全3回)です。
矢崎理恵さん(社会福祉法人 さぽうと21)に執筆いただきました。
最終回:地域で共に暮らしていく
さまざまな背景を持つ「難民」と呼ばれる方々。最終回となる今回は、日本で、地域で暮らす彼らに、同じ地域住民である私たちができることを考えてみます。その答えのヒントは、皆さんがよく抱く疑問の中にあるようです。

日本に10年以上滞在し、今は同胞の支援に力を尽くしているウクライナ出身のAさんが、この間、ため息まじりにつぶやいていました。

最近、ウクライナ避難民の支援に携わる日本の方から、こんな風に言われることが多くなったんですよ。『ウクライナの人は日本が気に入らないのだろうか。一生懸命やっているけれど、全然日本になじもうとしてくれない。』
そのつぶやきを聞いて、わたしはもう何年も前の、中東出身のBさんとのやりとりを思い出しました。
日本を選んだ理由
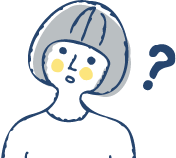
Bさんは、ご自分の家も車も残したまま、国を逃れなければならない状況にあったのですよね。どうして知り合いもいない日本に来ることにしたのですか。
Bさんは、こんなふうに答えました。
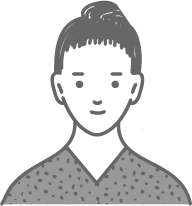
あなたが海で溺れ死にそうになっていると思ってください。そこに1つ小さな島が見えました。あなたはどうしますか?好きか嫌いかは関係ありません。とりあえず、その島を目指すしかないでしょう。だからわたしは日本に来ました。
そんな彼らに、私たちができることは何でしょうか?
気持ちに寄り添い、受け止めよう
母国を逃れ、何の備えもなく、国をこえて移動し、たまたまたどりついた国が日本だった、というのは、決して珍しい話ではありません。難民申請の結果を待つ間はもちろん、難民認定されたとしても、今はまだ目の前に何の光も見えていない人がいます。機会があれば、いつか日本以外の国に行きたいと願い続けている人もいます。皆さんの本当の意味での日本生活は、まだスタート地点についていないのかもしれません。
そんな人々の状況を理解し、その複雑な心情を受け止めてくれる職場、学校、地域であってほしいと、日々の難民の方々とのやり取りの中から強く感じています。「憐み」とか「同情」とかではなく、「職場・学校・地域で共に暮らす仲間」として受け入れる気持ちをもちながら、「ご自分の足で歩き出すタイミング」を、気長に待っていただきたいと思います。
気軽に声を掛けつづけよう
「おはよう、○○さん、いい天気ですね」と声をかけるぐらいのことから始めてみてください。はじめはことばが返ってこないかもしれませんが、声をかけ続けることが大きな支えとなります。大きな問題があれば、役所や難民支援団体に相談に出向き、解決をはかるだろうと思います。
でも、「ちょっとわからないこと」「ちょっと困ったこと」を気軽にたずねることのできる、同僚、クラスメイト、ご近所さんの存在こそが、皆さんの日々の暮らしを支え、日本社会を肯定的に受けとめられる糸口となることでしょう。地域で共に暮らす皆さんには、「いつでも声かけてね」のサインを出し続けていただければと思います。
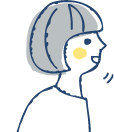
身近にできることから
始めてみるといいですね!
難民の皆さんにとって、この国は、好きでやって来た国ではないかもしれません。でも、いつの日か皆さんに「やっぱり日本に来てよかった」と思っていただけることを日々願って、活動を続ける毎日です。
(さぽうと21 矢崎 理恵)



